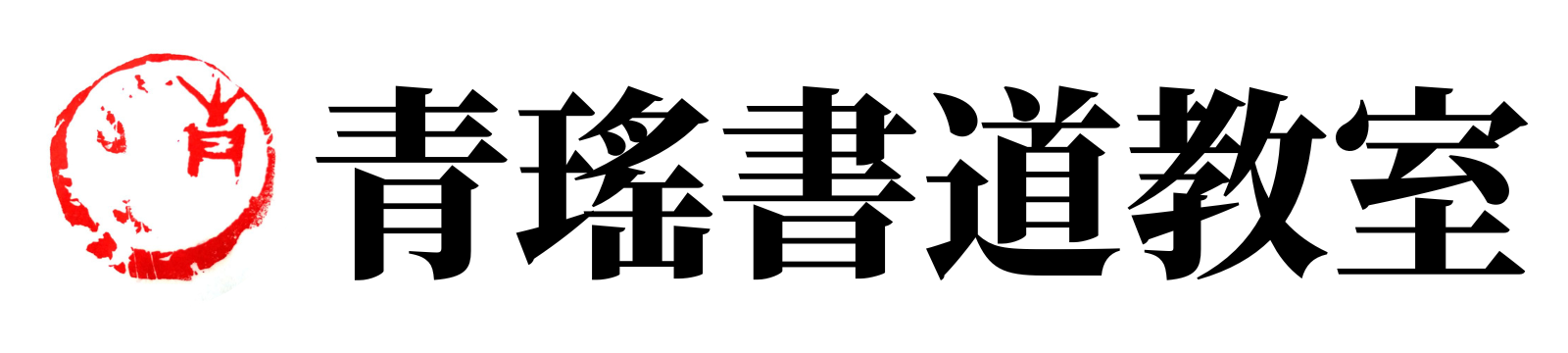書道展覧会を開催するためにやるべきこと【5ステップ】
(展覧会開催までの準備や流れとは。)

書家
片岡 青霞
プロフィール
書道教室を運営している先生方が、ご自身の教室の展覧会を開催してみたいと考えた時、どのような手順を踏んで開催までに至っているのだろうか。書道展覧会を開催するには、公募展も社中展もほぼステップは同様となるが、今回は社中展を開催するまでの流れや準備に関して紹介してみようと思う。ちなみに社中とは、一会派の同門生のみで行われる書道展のことで身内のみでの展覧会と考えていただければわかりやすいのではないかと思う。
①開催日程とコンセプトを決める
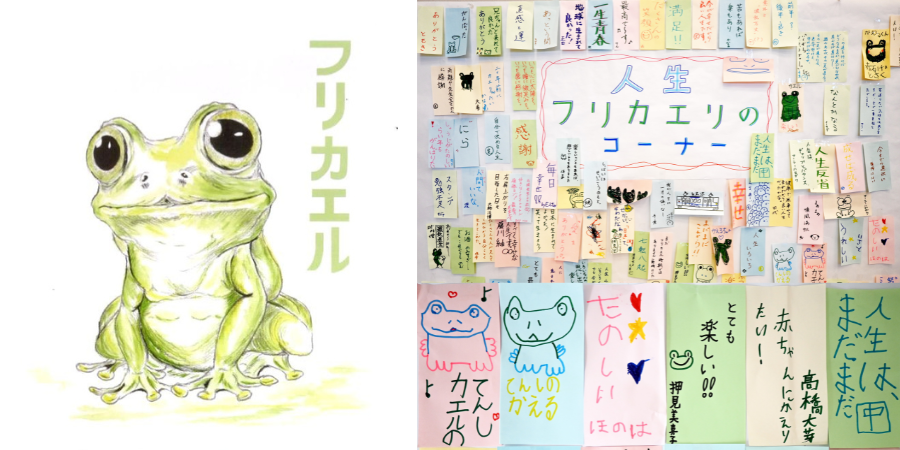
社中展を開催しようと考えた際にまず最初に決めることは、展覧会をいつ開催するのか。何年何月頃に開催したいのかの候補を決める。社中展を開催するにあたっては、何かと準備することがたくさんあるため、事前に大まかな開催時期を設定する必要がある。開催時期の決め方は、春夏秋冬の4つの区分けで決めたり、祝日を含む日程スケジュールを考えたり、子どもや大人の生徒さん、または先生の各種展覧会時期と重ならないようになど配慮することがいくつかある。これらのことを踏まえて最もよい開催時期を検討していく。
また、社中展を開催するにあたってはコンセプトやテーマなどを決めていない教室がほとんどではないかと思う。一つの社中展を通常通り定期開催することでも充分であるし特に何も問題はない。これは主催者がどのような社中展を開催したいのかの考えにもよるが、当教室は毎回のテーマやコンセプトを決めて社中展を開催をしている。その理由の一つに、毎回同じような展覧会にならないようにするためやテーマを決めることでの取り組みやすさがあげられる。社中展の開催は、毎年のように開催している教室もあれば、気が向いた時に開催する教室、数年間隔で開催をしているところなどさまざまとなっている。公募展主体として活躍している社中であれば、毎年の開催はかなりハードとなるが、実際にそのようにして取り組まれている教室もあるのだからとても感心させられる。ちなみに当教室は三年に一度の開催としているが、今のところ良いペースだと感じている。来場者の方々が見に来て楽しかった、良かった、明るく晴れやかな気持ちになれるようなそんな社中展を目指している。
②会場を決める

開催日とコンセプトが決定したら、次に社中展を開催するための会場を決めていく。会場は、どのくらいの規模の社中展を開催するかにより異なる。施設は、美術館、文化会館、コミュニティセンター、ギャラリー展示場などがあるが、公民館や図書館の一部を借りて開催することも場所によっては可能となる。大抵の施設の予約は一年前からとなっているところが多い。年間を通じて、都道府県主体で開催している大きな展覧会を除き、施設では抽選が行われているところがほとんどとなる。事前に開催日を決めても他の団体と施設を借りたい日程や場所が同じであれば抽選となる。そのため、希望日を抑えることができないこともあることを事前に認識しておく必要がある。どのくらいの団体や人数が会場予約のための抽選にくるのかは、施設やその月によってもばらつきがある。万が一、他の団体と被り抽選に外れてしまった時には、別の日程を再検討する必要があるため、公募日は複数用意しておくことが最適である。抽選は公平なものとして行われる。運やツキを味方にして希望日を抑えられるようにしよう。
③生徒さんへのご案内(作品書き)

開催日と会場が決定したら、生徒の皆さんへ社中展を開催するにあたっての要項をご案内する。社中展開催日から逆算をして、いつからご案内をし作品書きをしていくのか事前に決めておく。
書道展なので、一番肝心なものは書道作品となる。生徒さんが書く書道作品の素材決めからはじまり、実際に作品書きをする時間をある程度の期間設ける必要がある。当教室は、児童4か月、大人半年の期間を設けて作品を仕上げている。大人に関しては、年間を通じて公募展や展覧会主体で活動している団体であればもっと期間を短くして仕上げることも可能だとは思うが、当教室はそうではないためこの期間を設けている。なるべくいい作品を発表するためには、枚数を重ねる必要がある。半年間の期間を設けても、あっという間に感じる生徒さんがほとんどとなっている。通常のお稽古に加えて、社中展の作品書きが加わることになるため事前にどのようなスケジュールで取り組んでいくのかのご案内はなるべく早めにするようにしている。
④開催へ向けての準備
| DM (デザイン考案、発注) | DM発送作業 (宛名シール・住所書き) | 会場打合せ (必要用具の確認) | お弁当の発注 |
| 目録制作 (デザイン考案、出品者名前・作品名の確認、発注) | お花依頼 | 壁面計算 (展示ブース決め) | 書道作品の表装 (総点数の確認) |
| 立て看板 (完全原稿データ制作) | 写真パウチ作業 | 当番表の作成 (内容や注意事項など) | 必要備品の準備 (芳名帳、硯、筆など。) |
| ポスター | キャプション制作 | お茶菓子 | 打上げ店の予約 |
社中展開催日が近づくにあたり、準備することも同時にすすめていく。主に準備するものをリスト化して漏れがないようにする。大きな団体や社中ともなれば、準備そのものが大変な作業ともなるためお弟子さん複数人が中心となり作業をすることが多い。ご自身の作品書きをしながら同時に上記の準備もすすめていく。
準備には、自分たちで用意できるものとそうでないものがある。例えば、DMを制作するにあたりお弟子さんの中に印刷やデザイン関係を得意としできる方がいれば良いが、そうでない場合は、業者へ発注依頼をすることとなる。費用は生徒さんからの出品料から賄うため何にいくらかけるのかなど金銭面も考慮して準備にあたる。とくにDMや目録などは印刷前に誤字脱字、漢字相違がないかなど二重、三重にもチェックをしてから印刷へまわす。社中展の開催をするまでには、見えないところで結構な時間がかかることが多いので余裕をもって準備をすすめていこう。
| 御礼 (お返しの注文・発送、礼状書き、返信作業など。) | 書道作品の返却 (お預かりした書道作品、その他のものの返却) | HP(ブログ)への活動報告 |
| ミニアルバム制作 | 集合写真の現像 | 収支計算業務 |
また、社中展開催後にもやるべきことがいくつかある。来場いただた方々に対しての御礼を優先に、その後で書道作品返却、ミニアルバム制作や写真現像、HP(ブログ)への活動報告、収支計算などをおこなう。社中展を開催するだけではなく、開催を通じて良かったことや反省点、改善点などは必ず記載しておき、次回の展覧会へ繋げるようにしている。
⑤告知、宣伝
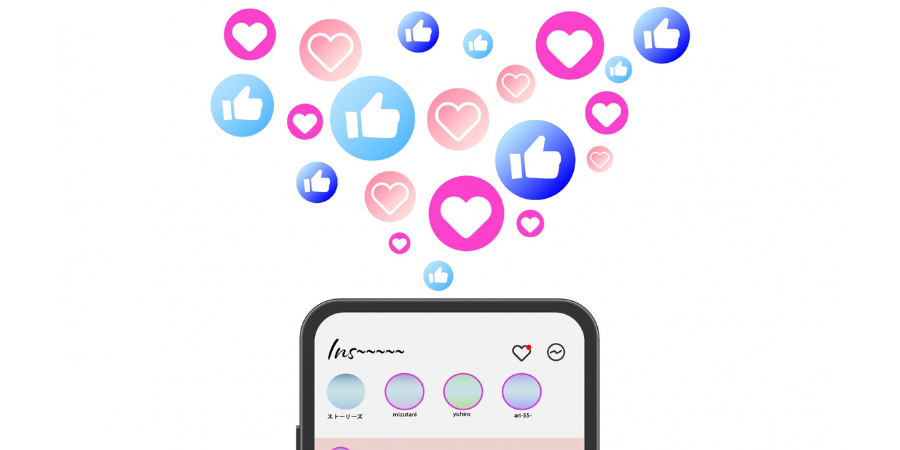
社中展を開催するにあたり、多くの人に作品鑑賞をしていただくために告知と宣伝をしていく。書いた作品をただ会場に飾ればいいということではなく、頑張って書いた作品をより多くの人に見て鑑賞いただくために、告知と宣伝は大切な役目となっている。方法は、ネットを使用したHP、SNS発信や、DMの発送、口コミなどがある。さまざまな形式で開催のご案内をしていく。
ほとんどの書道展では入場無料となるためご案内がしやすいことは書道展覧会のメリットの一つではないかと思う。大人になると生活環境が個々に多様化し皆が忙しい日々を過ごしている。仕事や家庭、プライベートで精一杯なため、何か用事がなければ人とゆっくりお会いして会話をするそんな機会は減っているのではないかと思う。誰もが主宰者にならなくても、主体的な活動をすることはできる。ご案内をすることで自らきっかけをつくり、このような社中展を通じて人との新たな出会いや交流が再開することがある。また、実際に来場された方々より、“ご案内ありがとう”と感謝されることも多い。主宰者のみならず、参加者全員でご案内をかける。告知や宣伝はとても重要なものとなっている。
今回は、社中展を開催するまでに準備することや流れを紹介してみた。皆で一つのものを創りあげる喜びはとても素晴らしいと感じている。はじめて社中展を開催する際はわからないことも多いかと思うが、皆で力を合わせて素敵な社中展を開催してみよう。