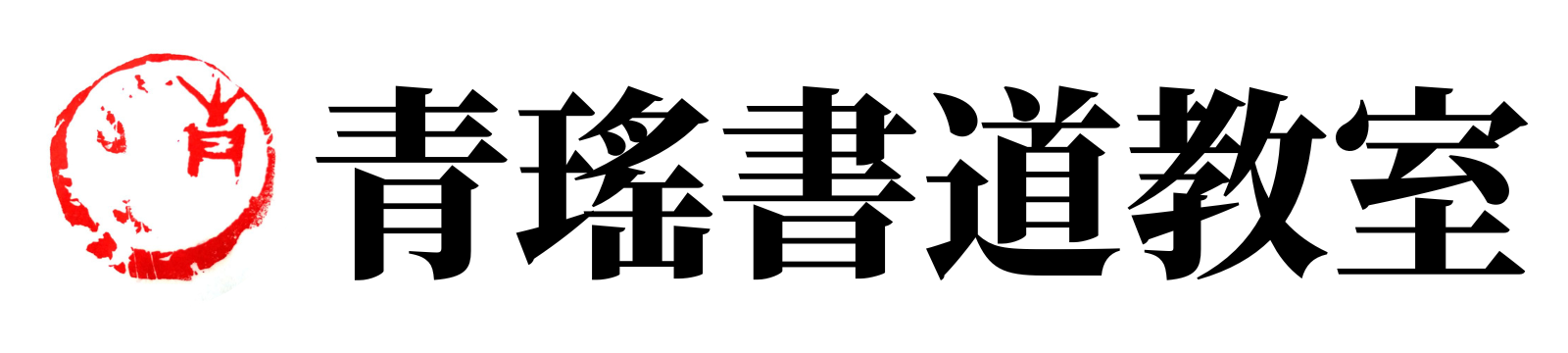「昔」と「今」を徹底比較。時代と共にかわる書道の学びの変化
(学び方、指導方法、用具の移り変わりについて)

書家
片岡 青霞
プロフィール
「見て学びなさい。」仕事にしても技術にしてもどのようにして身につけ習得するのか。昔ながらの考えの代表にあるものが、この見て学ぶではないだろうか。このようなスタイルが思わしくないとは考えておらず、むしろ肯定的な意見をもっているが、現代においてはそのような考え方は既に古く受け入れ難いと考えている人も少なくはない。果たして見て学ぶは既に古いものなのか。今回は、昔と今における書道の学び方が時代と共にどのように変化をしてきているのかということについて触れてみたいと思う。
「昔」と「今」でかわる、書道の学びの変化
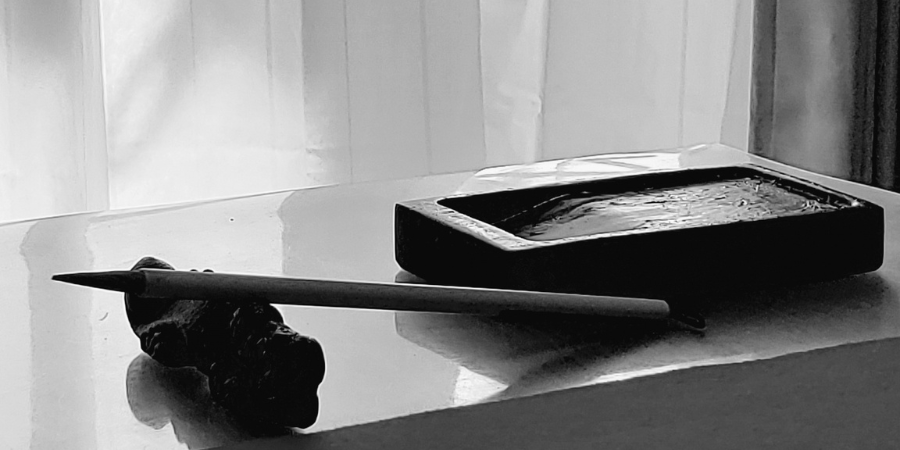
書道の歴史は古く、日本においては学校教育課程において誰もが一度は書道に触れたことがあるかと思う。学校教育だけではなく、さらに書道の学びを深めようと書道教室へ通われていた方々の学びは、昔と今でどのような変化を遂げてきているのだろうか。大きく分けると「学び方」「指導方法」「用具」の3つに変化があるのではないかと思う。
| 昔 | 今 | |
|---|---|---|
| 学び方 | ・対面のみ ・古典法帖、石碑 ・競書誌(教室団体) ・添削/お手本のみ ・教場では書かない(用具持参不要) | ・対面、オンライン ・古典法帖、タブレット ・競書誌(教室団体、個人) ・添削/お手本 ・教場で書く(用具持参必須) |
| 指導方法 | 模範型 | 教示型 |
| 用具 | ・硯 ・固形墨 | ・プラスチック ・墨汁 |
時代の変化を振り返ると、昔は物事の一つひとつを丁寧に時間をかけ丹精込めてつくられるものが多かった。物がなく不自由な時代を生きてこられた方々であれば尚更、物を大切に扱うのではないだろうか。戦後、目覚ましい経済成長を果たしたこの国は、現在物に困ることは限りなく少なくなった。わたしたちの生活は便利になったが、その一方でより簡単により早くを求めることで効率や即効性が重視される世の中へと移り変わった。これは、とても大きな変化の一つであり、普段の生活を取り巻く環境がこのようにして変容をしているということは、一つのことに時間やお金をかけることが薄れてしまっているのもいたし方ないことのように感じている。これらのことから、時代の中にある書道が変化をしたと考えるべきではないだろうか。
「学び方」「指導法」「用具」の3つがどのような変化を遂げているのか具体的に見てみよう。
①学び方(オンライン、競書誌、普段のお稽古)

書道の変化の一つに「学び方」がある。
書道の学びとしては教室へ通い直接の手習いが基本となるが、インターネットの普及により全国どこからでもネットへアクセスできる環境があればオンラインでお稽古を受講できるようになった。ネットは特に2000年代から急拡大をとげているが、2021年のニセのコロナパンデミック時からより活躍の場が広がった。オンラインで繋がっているので画面を通して筆の動きを見ることはできるが、やはりその場で感じる呼吸や緊張感、小さな動きにはかなわない。
書道を学ぶために競書誌を活用している方も多いかと思うが、自宅で個人でやられている方々もいる。教室へ通うにも都合がつかない人が、自分の隙間時間に書いて学ぶスタイルとなっている。昔は書道人口も多く競書誌にもたくさんの教室と氏名が連なっていたが、今ではかなり減少をしている。また、印刷費の高騰もあり競書誌の本体価格も値上がりしている現状がある。
昔ながらの大人のお稽古のスタイルは、自宅で書いた臨書や作品を教場へもちより、師匠から添削指導を受け古典法帖の新たなお手本を書いていただく形式であった。教場で筆を手にするのは師匠のみとなっており、他の方々が添削を受けている様子や師匠が臨書しているものを見て筆遣いを習得した。そのため普段のお稽古においては、書道用具を教場へ持参しその場で書くことがないため、他の方々が半紙(臨書)を書いている姿を見たことがなかった。そんな状態で果たして書けるようになるのかという疑問を誰もが抱くかと思うが、少なくとも自身はこのような学びをしてきた。今は教場で書いている教室がほとんどだとは思うが現代においてもこのスタイルは残っている。
②指導方法(模範型/教示型)

書道の変化の二つ目は「指導方法」となる。
指導方法には、「模範型」と「教示型」の2つがある。
「模範型」とは、行動を示して見て学べのスタイルで、多くを語ることなく見て感じて気づき自分のものにするという方法である。「教示型」とは、進め方や具体的な手順を細かく指導をする方法で、コスパやタイパを優先することで効率的に物事を進めるための方法となる。「模範型」は昔ながらのスタイル、「教示型」は現代的とも言える。
昔ながらの書道のスタイルは、この「模範型」によるお稽古をしてきたことになるが、臨書を持参しても丸しかもらえない、作品を見せても何もアドバイスが無いことが普通にあったという。ほとんどの方々が今このスタイルをされたら大半はすぐに教室を辞めることになる。その理由は、お月謝を払っているのに何も助言をしてもらえず指導がないと受け取る人がほとんどのためとなる。この内容だけであれば多くの方はそのように感じるかもしれないが、果たしてこのスタイルはほんとうに指導がないと言えるのだろうか。それでは、書道における観察力や洞察力、気づきはどのようにして身につけていけば良いのだろうか。昔ながらの指導は厳しいことが多く現代において同様のことをすればそもそも人がついて来れなくなることが大半だと感じている。そのため、丁寧に教えることになるが、だからと言って技術が身に付き習得できるようになるかは別問題となる。丁寧に教えても優しくしても辞める人はやめる。
これらは、書道のみならず会社での上司と部下のやりとりにも共通しているものがあるかと思う。上司が部下を育てるためにほとんどの職場では、「教示型」が採用されているかと思うが、指示以上のことはやらない気付かないことも多く頭を抱えている上司も少なくはない。
書道においても「模範型」から「教示型」への指導意向となっているが、これらをしたからといって人が育つとは限らない。別物であると考えるべきだと思う。
③用具(硯と墨)

書道の変化の三つめは、「用具」となる。
文房四宝の中でも墨における変化がもっともわかりやすいのではないだろうか。昔ながらの固形墨か、今の墨汁か。昔は、書道のときには固形墨を使用していた。煤と膠と香料を合わせて作られたもので、硯の上で水から磨り墨をつくる。墨磨り機がなかった当時は、家族の中に書道にどっぷりはまっている人がいるものなら家族総出で墨を磨っていたのだという。時間も労力もかかり大変なことだったと思う。現代、書道をやる方々においては硯や固形墨を使用する人の数は少なく、プラスチック容器と墨汁が圧倒的な割合をしめている。墨汁を使用する理由は、手軽で誰もが使いやすく、安価で時間短縮につながることがあげられる。昨今では、公募展や展覧会でほとんどが墨汁の作品となってしまった。墨汁を使用する頻度が高まれば、自然と硯も遠のくこととなる。老舗の書道用品店も硯や固形墨へのこだわりが強すぎるばかりでは経営がおもわしくなく、時代と共に墨汁やその他の商品へ力をいれて生き残りをかけている。
用具には相性がある。筆、墨、紙、硯の四宝があうことはいい書に繋がるきっかけとはなるが、現代においては時間や金銭が重視されるため昔ながらのスタイルは薄れつつある。書道教室をやられていても硯や固形墨がわからない講師は多い。使用していないのであたりまえと言われればそれまでとなる。
新しいものと継承されていくもの
時代と共に変わる書道の昔と今の「学び方」「指導方法」「用具」の変化をみてきた。時代のせいだけにはできないが、わたしたちを取り巻く大きな環境はこれからも変化していくことになるかと思う。その中でどのようにして書を学んでいくのかが問われている。すべてをただ新しくするのではなく、古き良きものは継承し改善すべきことは手を加えていく。どちらの時代にも触れたことがあるということは、もしかしたら恵まれているのかもしれない。これからも書があり続けることができますように。