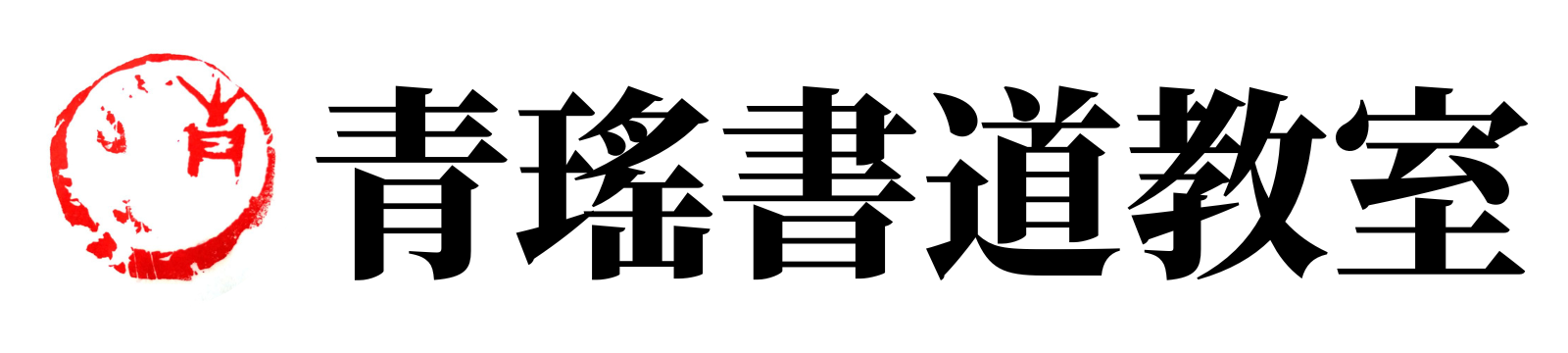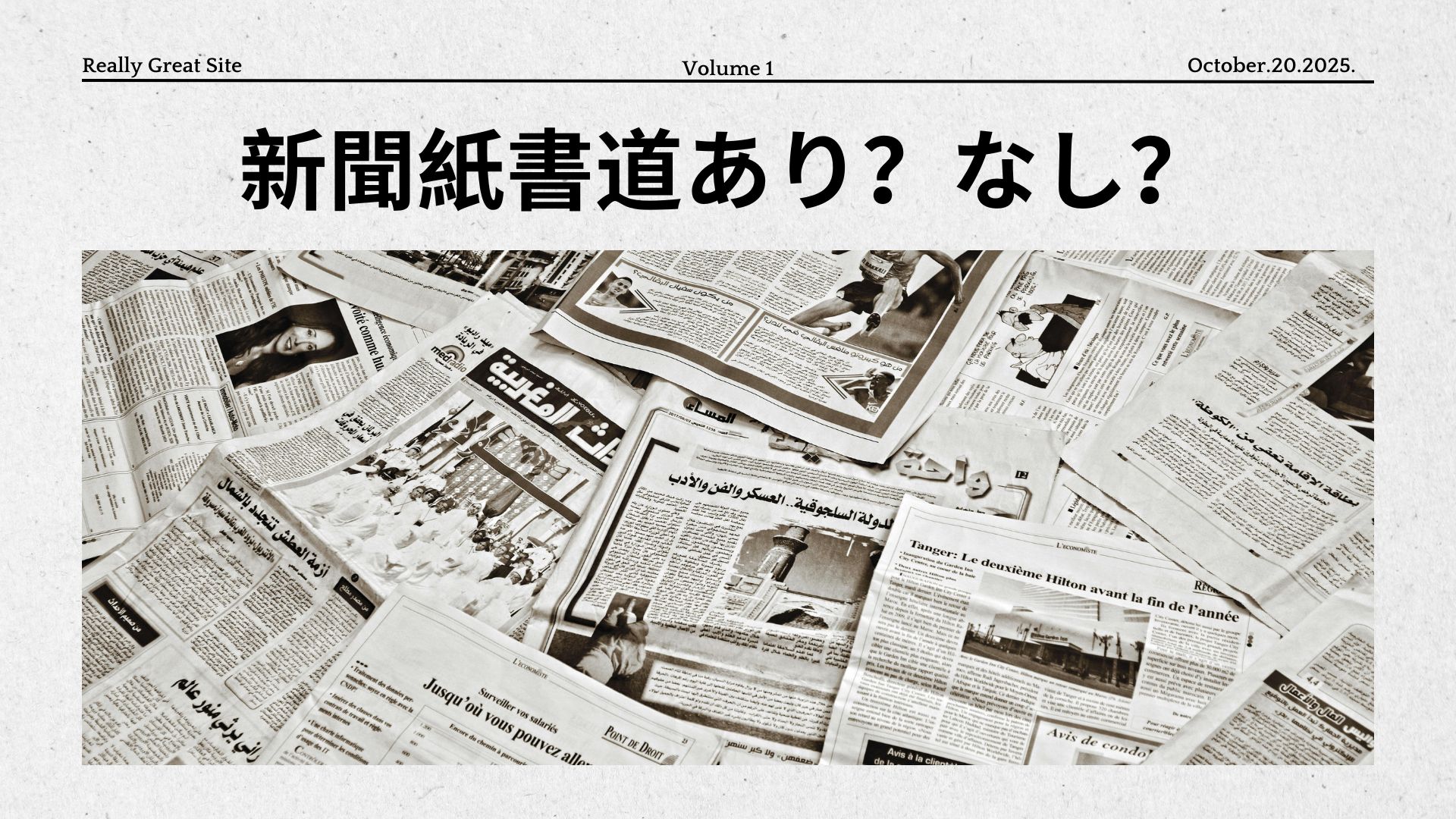
賛否両論。新聞紙に書道の練習はあり?なし?
(新聞紙を利用することでおこる弊害とは。)

書家
片岡 青霞
プロフィール
SNSを見ていると、書道のお稽古をしている動画の様子がタイムラインに流れてきた。 一見何ら変わらないお習字風景に思えた映像もよく見てみると、書道の練習のために半紙ではなく新聞紙を使用して文字の練習をしているのが目にとまった。異様な光景を目の当たりにし違和感しか感じなかったが、また別の動画でも同じようなものを目にしたことがあった。書道と言えば、真っ白な書道用の半紙を使用してお稽古をすることが一般的だと思うが、中には半紙の代わりに新聞紙を活用してお稽古をおこなっている教室がある。半紙ではなく、新聞紙で書道の練習をすることはありなのか、それともなしなのか。 この機会に皆さんも一緒に考えてみよう。
書の普及のために考えられた新聞紙による書道展
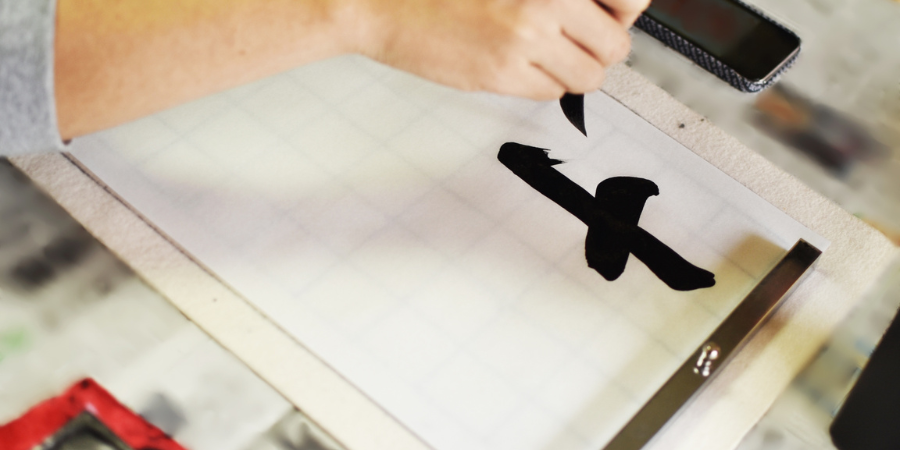
ここ数年で、少しずつ目にするようになった新聞紙に書道の練習をする光景。先に結論を述べるが、個人的には書道の半紙を使用せずに、新聞紙にお習字の練習をすることには否定的な意見をもちあわせている。理由はいくつかあるが一番に掲げるものとして、「本来の正しい書」というものから逸脱しているからに過ぎないためと言える。
書道業界に携わっていながら、最近になってはじめて新聞紙に書道の練習をしている教室があるということを知った。SNSには教室内でのお稽古の様子がUPされており、一つの教室だけではなく他にもあることがわかった。ここで取り上げているのは、たまたまワークショップとして遊びの一貫としてやっているのではなく、普段のお稽古から常に新聞紙にしか練習をせず、 逆に半紙を一切使わないという教室があるということである。最初に知った時は冗談かと思えたが、まぎれもない事実であった。真剣なまなざしでお手本を見ながら新聞紙に練習をしている子どもたちの光景はとても異様なものでしかなかった。ネタとかではなく、真面目に取り組んでいるのだから不思議で仕方がない。なぜこのようなことになっているのかということを少し調べてみると、新聞紙に書く書道展というものを発見した。読んで字のごとく通常の書道半紙に書くのではなく、新聞紙に文字を書いた書道展覧会の開催である。主催者の意図としては、 新聞紙に筆で書く楽しさを知ってもらうためと書かれていたが、書く楽しさを知るのであれば通常の書道半紙に書けばいいのではないか。という疑問が湧いてくるが皆さんはいかがだろうか。さらに一歩踏み込んで中身をみてみよう。
新聞紙を使用する理由

そもそも書道半紙を使用せずに、新聞紙で練習をしている理由は何なのか。最も考えられる理由としては、安価なものだからということがあげられるのではないかと考えられる。コストパフォーマンス重視のために、より手軽に身近なものを使用して書道をおこなっているということである。
書道半紙と言っても、さすがに昔に比べれば値上がりはしているが、それでも必要最低限のコストで練習はできるものとなっている。 今から30年前、 小学生の頃に通っていた書道教室では半紙20枚60円の値段であった。 今現在、当教室で販売しているのは半紙20枚100円となっている。たしかに30年前と比べれば現在は物価高で40円の値上がりになっているが、それでも100円でその日のお稽古を真っ白な半紙に書けるということは、素晴らしいことではないかと思っている。 実際の半紙に筆で書いたものと新聞紙に書いたものとでは書き心地に差が生じる。書道半紙を使用することは、本来の正しい書のあり方やその姿を映し出すことへも繋がっている。
以前、私自身が通っていた教室で通信のお稽古をしている方が新聞紙に臨書を書いて先生のもとへ郵送をしてきたことがあった。ネタなのかとさえ思えたが、本人はいたって真剣で真面目に臨書をして師に添削を求めてきたのだからとても驚いた。この行為は師に対して大変失礼なことであり、書に対しての敬意を感じることができず、例え金銭が厳しくてもいかなる理由においてもこのようなことは決してしてはいけないと感じた出来事であった。
なぜ新聞紙を使用してはいけないのか
書道半紙を使用せずに新聞紙を使用することは、価格の問題だけではないことが言える。他にどのような理由が考えられるのだろうか。
もっとも重要なものとして、「本来の正しい書」というものから逸脱しているためと言えるが、 ここで述べる正しい書とは、書道を学ぶにあたって使用する本来の書道用具を用いておこなう書のことを指している。文房四宝としてあげられる、筆、墨、紙、硯の4つは書道を学ぶ上において欠かせないものとなっている。筆に墨をつけ文字を書く時に最も適しているのが書道半紙なのであって、間違ってもこれが新聞紙になることは考えられない。四宝がかみ合うことで、はじめて書道と言えるのではないだろうか。これらは古来、書に携わってきた方々がとても大切にしてきた用具と言える。正しい書を子どもたちに教えることは、学校関係者や書塾の先生方による大切な役目となっている。これは、教育上の問題としてどうかが問われている点でもあるということを念頭に置いておかなくてはいけない。
書道をやるということは決して書くということだけではなく、文字について学び理解を深めるということに通じている。 文字を扱う者が上から文字を塗りつぶすような行為に対して甚だ疑問を感じている。新聞紙に書くことで筆が摩耗してより傷みやすいということを述べている方もいる。 通常の半紙による本来の書き心地がわからず、そうでないものに慣れてしまっているその感覚に関してはどうだろうか。幼い頃に身についた感覚を大人になってから改めようとすると時間がかかることは誰もが何かしらの形で経験があるのではないだろうか。正しい鉛筆の持ち方を子どもの頃に向き合ってこなかったために、大人になってから恥ずかしい思いや苦労をしている人もいるだろう。このような理由から、新聞紙に文字を書くことには同じ書を志す者として、否定的な意見をもちあわせている。
最も美しい書の世界

書道の展覧会や公募展へ向けて作品書きをしている時に、カラーバリエーションのある色付きの加工紙に書いて作品を出品したことがある。練習は通常の白色で取り組み、後半になって作品を仕上げるにあたり色付の加工紙を使用するという方法である。仮名であれば、料紙もたくさんありどのような作品にするかの幅がより広がるかと思うが、漢字も同様に加工紙を使用して作品を仕上げることができる。色付加工紙を使用することで、よりインパクトを与えたり、素材を引き出す効果などもあり、適した方法として活用されている方々も多いのではないかと思う。
だがその一方で、こんな話を聞いたことがある。
“現代においては、さまざまな加工紙が販売されていて、作品以上にインパクトが強い紙がある。そうすると、本来の素材というものに目が届かずに紙だけに目がいくようになってしまう。展覧会や公募展というのは、たくさんの作品の応募の中から選出されるためにどうしてもインパクト重視のところもあるが、これらは本来の書というものとは少し異なる。作品書きの後半で加工紙に書いて、ほんとうにそれが良くて選ばれたのであればいいが、 最終的には白紙に戻って作品を書いてみるのがいい。漆黒が最も引き立つのは反対色。だからこそモノトーンの世界は美しい。”
誰が言ったのかさえも思い出せないが、さらっと聞いた言葉がとても印象的に思えた。書の本来の美しさとは何か。改めて考えさせられる言葉であることには変わりないのではないだろうか。